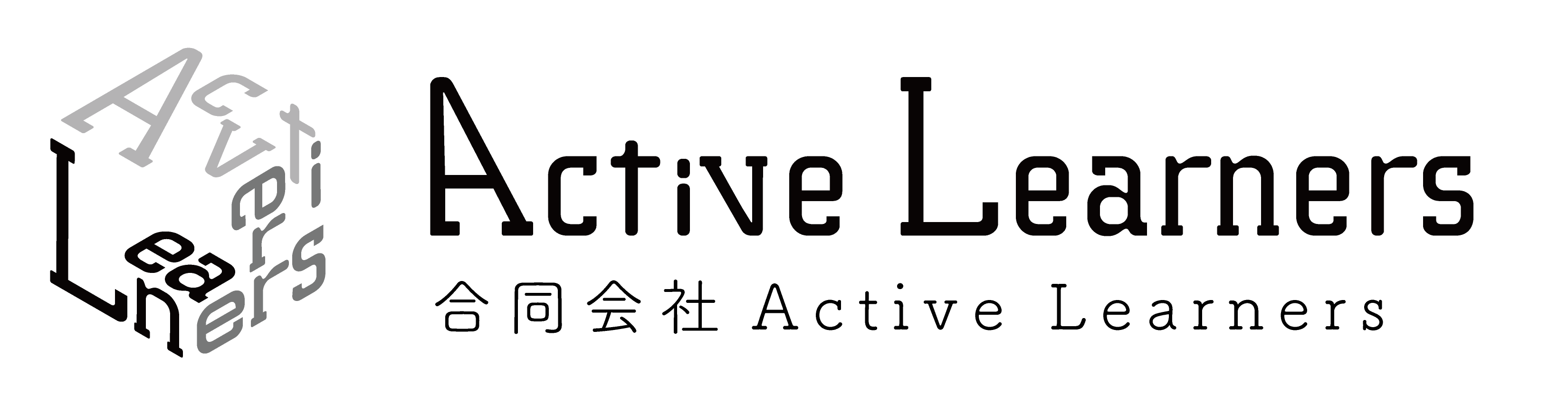主体性を促す場のつくり手のみなさんで「主体性とはなにか」を考える@目黒青少年プラザ
5/12(日)に、目黒青少年プラザのスタッフ研修会のファシリテーターを担当させていただきました。

スタッフのみなさんが普段企画・運営されている講座の目的は、「知的障害のある参加者が、学習活動の支援を受けて自主的に社会に参加し、より豊かな生活を送るための力を身につける。日常の社会生活の中で主体的に活動できるようにする」こと。
例えば、ある参加者の状態をAさんは「放置されて困っている」と捉え、一方でBさんは「それも主体的に学んでいる最中だ」と捉えたり。
その結果、参加者への関わり方の違いにお互いにモヤモヤしたり、講座の評価指標がバラバラであることが課題でした。
本研修では、みなさんの想いや考え、捉え方の違いを聴き合いながら、改めて自分なりに「主体性・主体的とは何か」を言語化することで、スタッフとして参加者にどう関わっていくかを考える機会をつくりました。
アクティビティはワールドカフェをチョイス。
第1ラウンドでは、「講座の参加者の主体性が発揮されたと感じた瞬間・出来事は?」とこれまでの講座を振り返りながら共通認識を広げました。
第2ラウンドでは、「主体性が発揮された時の環境は?何をした?何をしなかった?」ということで、メンバーを入れ替え、第1ラウンドの話を参考に主体性が発揮される場の要件について考えました。

そして第3ラウンドでは、元のテーブルに戻り、これまでのお話を踏まえて「主体性・主体的とは〜である」という「自分辞書」を作成し、共有・意見交換しました。
弊社も『クリエイターズプロジェクトめぐろ』という、小中学生がダンスの発表会を1から作り上げるお手伝いをするという事業を3年間担当させていただきましたので、そこで参加者の主体性を促すために意識していた「スタッフ、参加者全員でゴールを共有してから進める」「小さく低いステップから始め、徐々に手放していく」「ゴールは変えてもOK」という3つのことを共有させていただきました。
みなさま、本当に熱い想いをお持ちの方ばかりで、これまでのご経験をたっくさん話してくださったり、一方でスタッフ経験の長い方が短い方に積極的に話を振るなどの思いやりも見られました(#^^#)
終了時には全員が自分辞書を完成・共有することができ、無事にゴール達成!
今後は違っていることが当たり前・大前提として、講座の前後に丁寧に話し合ったり振り返ったりしながら運営していくことをご提案して終了しました(^^)
アンケートでも非常に好意的なご意見を多くいただき、多くのスタッフがこのような話し合いの場を求めていたことが伝わってきました(講座担当者さん、ナイス!!!)
午後はより具体的に参加者の主体性を引き出すための講座の運営方法について検討するそうです。
みなさん、お疲れ様!&引き続きファイトです!!!

〈ゴール〉
「主体的・主体性」のイメージが自分の中でなんとなく言葉にできるようになっている
〈プログラム〉
1.開会・前提の共有「本日の主旨、ゴール、プログラム、グランドルールの共有」
2.アイスブレイク「チェックイン・自己紹介」
3.グループワーク「ワールドカフェ〜3ラウンド」
4.振り返り